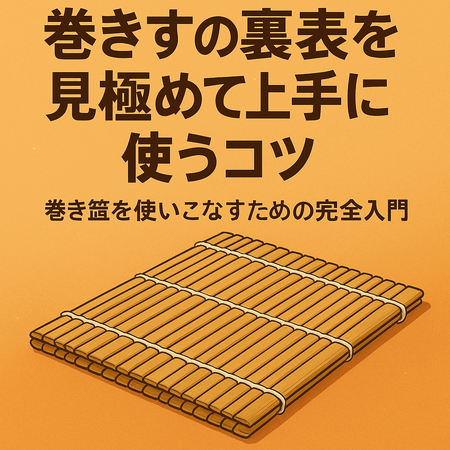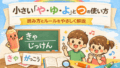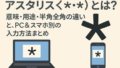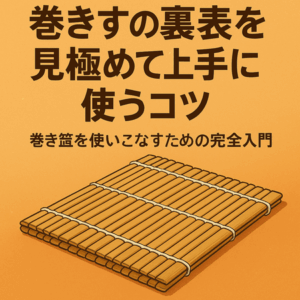
巻きすとは?巻き簾との違いはあるの?
巻きすは、竹やプラスチックなどで作られた細いひごを糸で丁寧に編み込んで作られた昔ながらの日本の調理道具です。巻き簾(まきすだれ)とも呼ばれることがあり、呼び名は違っても用途や構造はほぼ同じ。主に巻き寿司や伊達巻などを形よく仕上げるために使われ、プロの料理人だけでなく家庭でも親しまれています。また、料理の形を整えるだけでなく、見た目を美しく演出してくれる名脇役でもあります。
巻きすに「裏表」がある理由
一見どちらも同じに見えますが、実は“表”と“裏”が存在します。これは、竹ひごの丸みの向きや糸の結び目の位置によって決められており、見た目の仕上がりや食材のくっ付きにくさ、巻きやすさに大きく関わる大切なポイント。正しく使い分けることで、料理がグッとお店のような仕上がりになるのです。
巻きすの「表」「裏」の見分け方
見た目でわかるポイント
・丸くつるんとして光沢のある面 → 表面(食材に触れる面) ・糸の結び目が出ていて凹凸がある面 → 裏面(外側になる面)
覚えやすいコツ
“つるつる=表、ボコボコ=裏”という語呂に加え、料理する際は「きれいな方が食材側」と覚えておくと安心です。また、結び目がある方は裏と決め打ちしておくと迷わずに使い分けができます。
間違えるとどうなる?
裏面を食材側にしてしまうと、竹の糸の凹凸にごはん粒が入り込みやすく、仕上がった巻き寿司がはがれにくくなったりボロッと形が崩れてしまうことがあります。さらに、竹の模様がはっきりつき過ぎて見栄えが悪くなるため、せっかくの料理が台無しに。正しい面を使うだけで見た目の美しさも食べやすさもグッとアップします♪
正しい使い方|結び目と向きに気を配ろう
結び目は外側(下側)に置く
巻きすを使うときは、まず“結び目の位置”を意識しましょう。結び目がある面は裏側とされ、調理中は下(外側)にくるように敷くのが基本です。表面が食材に当たるように置くことで、仕上がりが美しくなり、ごはん粒などが糸に絡みにくくなります。
巻き寿司を作るときのポイント
すし飯をのせる面は必ず「表」。そのまま使うとくっつきやすいため、全体を軽く水で湿らせておくと作業しやすくなります。海苔をのせ、すし飯を均一に広げる際は、手前に厚め、奥に薄めを意識すると美しい渦巻きになります。
伊達巻・卵焼きの場合
伊達巻を作るときは、卵液を均一に焼き上げたあと、焼き色を外側にして巻きすで巻きます。模様を付けたい場合は竹の凹凸を活かすために裏側を食材側にすることもあり、見た目の仕上がりを重視するときは“あえて裏面を使う”のがプロのテクニックです。
模様をつけたいときのコツ
巻き終わったらすぐに巻きすで包み、表側でぎゅっと押さえながら形を整えます。少し時間を置いてしっかり冷ますと、竹の模様がくっきりとついて見栄えの良い仕上がりに。余熱を利用して形を固定するのもきれいに作るコツです。
巻きすの材質による違いも覚えておこう
竹製とプラスチック製の違い
・竹製:昔ながらの風情があり、本格的な香りと見た目を楽しめます。適度な柔軟性があり、食材の形を整えやすいのが魅力ですが、水分を吸収しやすいため丁寧なお手入れが必要です。 ・プラスチック製:軽量で扱いやすく、洗剤でサッと洗えて乾きも早いので忙しい方や初心者さんに人気。衛生的に使いやすい反面、竹のような風合いはやや劣ります。
初心者さんにおすすめは?
まずは扱いが簡単でお手入れもしやすいプラスチック製から始めてみるのがおすすめです。慣れてきたら、香りや風合いを楽しめる竹製にステップアップすると、巻きすの魅力をより深く楽しめます♪
巻きすがないときの代用品は?
ラップやキッチンペーパーで代用
薄めの巻きもの(例:野菜巻きや薄焼き卵など)であれば、ラップを使えばある程度きれいに形が整います。また、キッチンペーパーを下に敷き、その上にラップを重ねて巻くことで、滑りにくくなり扱いやすくなります。さらに、タオルやシリコンマットなど弾力のあるものも代用可能で、しっかり力を入れて巻きたいときに便利です。
代用品を使う際の注意
巻きすほどの弾力がないため、形が崩れやすく、横から具材が飛び出してしまうこともあります。巻くときは、生地を強く押さえながらゆっくり丁寧に形を整えるよう意識しましょう。完成後はラップごとしばらく包んでなじませると、崩れにくくなります。
よくある失敗と対策
ごはんがくっついてしまう
裏表を逆にして使ってしまうと、竹ひごの凹凸にごはん粒が入り込んで取れにくくなります。使う前に表裏を確認し、軽く水で全体を湿らせるだけでも、粘り気が抑えられてくっつきにくくなります。また、作業中に水を少し手に付けながら進めると、より扱いやすくなります。
巻きがゆるくなる
巻く力が弱いと、仕上がりがゆるんだり、具材がはみ出す原因になります。両手で均等に押さえながら、手前から奥にしっかりと力を込めて巻き上げるのがコツ。初心者さんは最初だけラップで包んで形を整えてから巻くと失敗しにくくなります。
カビが生える!という方へ
竹製の巻きすは水分を含みやすく、湿気が残るとカビの原因になります。使用後はできるだけ早くぬるま湯で洗い、布巾などで表面の水分をふき取ったあと、風通しの良い場所で完全に乾燥させるのが長持ちの秘訣。定期的に天日に当てて乾燥させてあげると衛生的です。
洗い方・保管方法
使用後はできるだけ早めにぬるま湯で竹の間の汚れを落とし、汚れがひどい場合は柔らかいブラシで優しくこすり落とします。洗ったあとは布巾で水分をしっかり拭き取り、風通しの良い場所で陰干しし、完全に乾いてから収納します。湿気がこもるとカビの原因になるため、保管は引き出しではなく吊るしておくのもおすすめです。
動画で学びたい方へ
YouTubeには「巻き寿司の巻き方」「伊達巻のプロ技」など調理の動きを丁寧に説明してくれる動画が多数あります。文章だけでは伝わりにくい“手元の使い方”や“巻き始めの力加減”が一目で分かるので、初心者さんは特に動画を活用するのがおすすめです。お気に入りのレシピ動画を保存しておけば何度も見直しでき、繰り返すうちに自然とうまく巻けるようになります。
まとめ|巻きすを味方につけて料理上手に♪
巻きすは上手に使いこなせるようになると、ご家庭の料理がワンランクアップします。裏表の違い、巻く向き、材質や使い分けを意識するだけで、見た目もきれいに整い、味わいもより豊かに感じられるようになります。ぜひ日々の食卓でいろいろな料理に活用して、巻きすの魅力や楽しさを実感してみてくださいね。